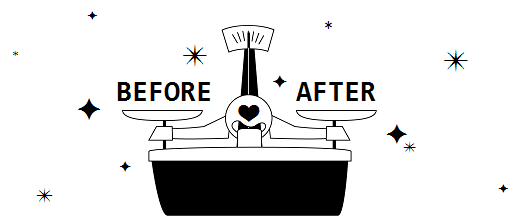
「光ちゃん。光ちゃんてば。ねえ起きて」
眠りこける彼氏の肩をゆっさゆっさと小さく揺らしてみるけれど、肝心の光ちゃんはテーブルにうつ伏せになったまま一向に目覚めようとはしない。…いや、きっと夢の世界から戻ってきてはいるんだ。確実に。だって横顔から見る光ちゃんは眉間に皺を寄せていてまるで起こしてくれるなと言わんばかりのオーラを放っているし、「んー…」なんて気のない返事をだるそうな声で寄越してくる。かと思いきや、もはや放っておいてくれと言わんばかりに体勢を変え、テーブルの上で組んでいた腕の間に顔を埋めるように隠してしまった。
「…あっ」
可愛い横顔が見えなくなっちゃった。思わず声が漏れてしまったところでいや今はそこじゃないと慌てて邪念を振り払いつつも、もはや後頭部しか見えない光ちゃんにどうしたものかと考え込んで早数分が経過している。そもそも事の始まりは、欠席者もいたもののほぼフルメンバーで開催されていた私と光ちゃんが所属するサークルの飲み会だった。某有名チェーンの居酒屋に予約された団体用個室で2時間ほど前からまるで祭りのようにどんちゃん騒ぎを決行しどんどんテンションが高まった一同は、次の日が土曜日というのをいいことにひたすら飲酒やハイテンション特有のトークに走り、もはや収集がつかない状態になっていた。
そんな中飲み会独特のノリに唯一流されることなく自己のペースを守っていた光ちゃんも、アルコールをちびちび飲んでいた、ように記憶している。…何気なく彼を見てみたとき、なんかいつもに増して不機嫌そうな顔をしてるなあと思ってはいたんだ。でも光ちゃんもともとああいう顔だしな、と大変失礼なことを考えそのまま放置し、そして気がついたらいつの間にか彼は中学から健在していたマイペースっぷりを見事に披露してテーブルの隅で突っ伏して寝ていた。というわけだった。
…こういうの知り合いがいないとこでやったらKYだなんだって叩かれるからね光ちゃん。しかも1年生で。良かったね昔からの知り合いである私がいて。君が寝ている間、「―、旦那が寝てるよー」とあちこちから冷やかされネタを振られてたんだからね光ちゃん。ついでに邪魔者が寝てるということもあってかいつから付き合い始めたんだとか告白はどっちからなんて言ったんだとか検索も始まって大変だったんだから。貸しだからね光ちゃん。…まあそのときは気遣いの出来る幹事くんのフォローもあってなんとかなったんだけど。
「先輩、財前どうです?起きました?」
私達がなかなか来ないことを心配したのか廊下から様子を伺うようにひょこりと顔を出したのは、やっぱり中学からの顔見知りの白石くんだった。彼は大学が違うとはいえ私と同じインカレのテニスサークルに所属しているから、今日の飲み会も必然的に出席していた。白石くんは中学のときから大人びていたけれど大学生になった今でもその気遣いは健在で、酒に飲まれてしまったメンバーの世話係に回ったりなくなった酒の注文を行ったり先輩から付き合わされた愚痴話を人の良い笑みを浮かべながら「そうですねえ」なんて言いながら聞いてやったりと色々忙しそうにしていたものだから、ちっとも呑んではいないはずだ。でも本人いわく「呑めないわけじゃないけど、特別好きというわけではない」らしいから、白石くんにとってはいい逃げ道を見つけたと思っているのかもしれない。そんな彼は相変わらず突っ伏している光ちゃんの姿を見つけ、「あー、まだ寝とるんかいな」と独り言を漏らしながら、どうしたものかと頭を掻いていた。
「行ける奴だけで2次会行こうって話になったんですけど、その様子じゃ無理そうですね」
「うん。だから私、光ちゃん送ってくよ」
「すんません、そうして貰えると助かります。本当は俺が送るべきやとは思うんですけど、今日俺幹事なもんで抜けられそうにないんですわ」
申し訳なさそうに眉をハの字に垂れ下げる白石くんに、真面目だなあなんて思いながら「大丈夫だって。どうせ電車の方向同じだし」とフォローすると、廊下から「白石―」と大きな声で彼を呼ぶ男子の声が聞こえてきた。どうやら他のサークルメンバーが、白石くんがなかなか来ないことに気付いたらしい。慌てて廊下に顔だけ出して「先行っとってー!」と大声で返す白石くんの背中に、思わずふふっと笑みが零れる。白石くんはどこに行っても人気者だ。
「白石くん。みんな呼んでるみたいだし行っておいでよ。幹事がいないと困っちゃうでしょ。…私達もすぐ帰るから大丈夫。ありがとね、お疲れ様」
そう一声掛けると白石くんは振り返りやっぱり心苦しそうな顔をしていたけれど、自分が幹事であることもあってか素直に聞き入れたらしい。「ほな、お疲れ様です」と挨拶を寄越し、私達より一足先に部屋を出た。おそらくそのままエスカレーターに乗りこんで、他のサークルメンバーの待つ外へ向かったのだろう。
白石くんを送り出すと途端に静かになった室内は、スピーカーから流れ出す無駄にアップテンポなBGMと隣の部屋から聞こえてくる笑い声が聞こえてくる。…さて、と。私の役目はまだ残っていると言わんばかりに振り返り、ピアスの彼に近づいて再びゆさゆさと肩を揺らし始めた。…私達もいい加減帰らないと、店員さんにお声を掛けられてしまう。
「光ちゃん、もう飲み会終わったよ。みんなもう帰るって。2次会あるっていうけど光ちゃんは帰ろ。だから起きて。一緒に帰ってあげるから。ね」
「んー…おれもう少しねてから帰りますわ。……ねむいんで」
「だーめ!飲み放題の時間終わっちゃったんだから。次の予約の人達来ちゃうでしょ」
だからとりあえず外行こう外!と言わんばかりに無理やりテーブルから引っぺがしてみるけれど、なるほど光ちゃんはまるで早朝であるかのようにぼーっとしている。おまけに、わふうと大きな欠伸をしたけれど目は醒めないらしい。重そうな瞼は今も健在だった。…光ちゃん、お酒そんなに呑んでたっけ。そもそも光ちゃんはまだ大学1年生で未成年だから本当はアルコール呑んじゃだめなのだけれど、実質サークルに入ってしまえばそんな法律あってないようなものだった。でもお酒強そうな顔してるくせに実は凄まじく弱いだなんて、これは誰が予想出来ただろうか。いや、下戸って意味の弱いというか、お酒を呑むと眠くなる体質と言う意味の弱いと言うか。あ、でも意味はほとんど一緒なのかな。どうなんだろう。
「ほら光ちゃん、コート着させたげるから。ね。だから腕ちょっと上げて」
「んー…」
そう言って、大人しく寝かせてくれというオーラを全身から放っている光ちゃんを立たせ、年末年始のセールで「絶対光ちゃんに似合うから!」とゴリ押しして半ば無理やり買わせた個人的にお気に入りのグレーのダッフルコートを羽織らせる。…うん、我ながらいい見立てだと思う。やっぱり光ちゃんによく似合ってるよこのコート。…なんていうのは置いといて。…私、まるでちっちゃい子のお世話するお母さんのような気分でいる気がする。どうなんだろうこれ。けれどその大きな子どもくんはコートこそ着たものの、相変わらず隙を見せれば夢の世界に逆戻りしてしまいそうな雰囲気を持ち合わせていたものだから思わず肩をすくめた。…だめだこりゃ。
「光ちゃん。ねむい?」
「んー……」
眠たそうに瞼を重たくしている光ちゃんは目をこすり、無言と言う名の肯定を示した。なんだか子どもみたいな仕草に可愛いなあなんて思う反面「お酒弱すぎだよ」なんて心の中で突っ込んだりと、今の私はある意味非常に忙しい。まあ頭が痛い気持ちが悪いとかとか泣き上戸になるとかじゃないからまだマシといえばマシだけれど。ていうか介護するのが彼女って、よくよく考えれば普通逆なんじゃないだろうか。ポジション的な意味で。…ごめんね私お酒強くて。
「光ちゃん。気持ち悪いとか、頭痛いとかはない?大丈夫?」
「んー…」
相変わらずゆるーい返答しか寄越さなかったものの、気だるそうに頷いた。じゃ、とりあえず戻したりはしないのかな。よかった。とりあえず彼はひたすら睡魔に襲われているだけらしい。じゃあ帰れるかな。光ちゃんは財布もケータイもポケットに入れていて鞄持ってきてないとはいえ、一応コートのポケットに手を突っ込ませて頂いて、中身を確認してみる。…うん大丈夫、両方ある。それを確かめた私は自分のバッグを肩にかけ、光ちゃんの左手を引いて店を出た。…で、そのまま一直線に最寄りのJR駅に向かい無駄なルートを辿ることなく光ちゃんの城という名の家に到着し今に至る。
大学に入学した彼は3月の終わりからここで一人暮らしを始めている。駅から徒歩5分だし、ていうか1Rじゃなくて1Kだなんて相変わらずいいとこに住んでるなこのぼっちゃんめなんて思いつつふと彼を見やると、外の風に当たったというのに相変わらず夢の世界にこんにちはしそうな光ちゃんがやっぱり眠たそうに目を擦っていた。…かわいい。……じゃなくて。
仕方がないので部屋の一番奥に配置していたシンプルな黒のベッドに寝かせてみたけれど、まったく自分の家に着いたというのに、その主人は一向に私の右手を離そうとはしない。電車の中でもずっと。…あまえんぼだ。なんかうれしい。思わずにやついてしまう頬を必死に引き締めてみるけれど、一向に効果が現れないのはなんでなんだろう。
「光ちゃん。おうち着いたからね。私帰るよ」
膝を折って目線を彼に合わせつつそう話し掛けてみるけれど、やっぱり光ちゃんは手を離そうとはしない。眠いんじゃなかったのかと思わずにはいられないほどぎゅっと握りしめてくるものだから、珍しいこともあるもんだと半ば感心した。彼は手を繋ぐのが苦手で、だから私からねだったりしない限り手をとってはくれない人だったというのに。むしろ、「手繋ぐならキスしますわ。そのほうが手っ取り早いでしょ」と、一体全体何がどう手っ取り早いのかは分からないことを彼が中学生のときさらりと言われたことがある。…にも関わらず、一体どうしてしまったのか。…さっきの居酒屋でどことなく可愛い素振りと言い、お酒の力ってすごいなあと改めて実感する。だってほら、こうやって頭撫でても怒らない。うわすごい。いつもだったら「子ども扱いすんなや」と不機嫌になるのに今日はならない。うわすごい。ミラクルだ。
「……せんぱい」
「ん?なあに?」
あっしまった、つい赤ちゃんを可愛がるような甘い口調になってしまった。光ちゃんがデレたと内心きゃっきゃしている私も、実は今そんな光ちゃんにデレデレしているらしい。なんてことだ、これじゃ収集がつかない。状況が状況なだけに、私だけでも冷静に、かつ落ち着いた大人の対応をしなければいけないというのに。しかし光ちゃんが私のことを先輩と呼ぶのは中学生のとき以来で、だからつまり何が言いたいのかというと、懐かしい呼び方をされて私は今非常に懐かしく、かつ中学校に入ったばかりの幼い光ちゃんを思い出してにこにこしていた。最近はめっきり格好良いポジションに立っていると思っていたけれど、やっぱり内面は可愛いんだな、光ちゃんは。そんな彼氏くんは相変わらずぎゅっと私の手を握りしめたまま、ぼんやりとした口調で話し掛けてきた。
「……せんぱい。かえらんとってください」
「えっ…?」
「……そばにおって」
「えっ」
「…さみしい」
「えっ!!」
そ、そんな素直なこと言ってくるなんて、ほんとどうしちゃったの光ちゃん頭打っちゃったの!?驚きのあまり本気で爆発してしまうかと思ってしまった私は、もはやなんて返したらいいのか分からずぽかんと口を開いたまま間抜けな顔をするしかない。その代わり、君は本当に光ちゃんなの、とか、頭でも痛くなってきちゃったの?とか、そんなことを口を突いて出そうになったところを慌てて押し返してとどまらせた。
「(ひ、ひかるちゃん。どうしよう、かわいい)」
ていうか本当、どうしちゃったの。何度でも言うけれど。…今日は随分珍しく、いや、珍しいなんてレベルではなく、天変地異でも起こるのではないかと思わずにはいられないくらい甘えんぼさんだね光ちゃん。もう一回言うけど、どうしちゃったの光ちゃん。アルコール入ったからってキャラ変わりすぎでしょうよ。…と、思わずぶつけてしまいたくなるツッコミを心のうちで繰り返す。うっかりきゅんとしちゃったよ、なんてことも胸の中に秘めておこう。
でもだって、光ちゃんとは中学からの付き合いだけれど、こんなドストレートに甘えられたこと今まで一度だってなかった。何これメロン記念日ならぬ光ちゃんが甘えてくれた記念日ですか。…全然ギャグうまくないけど、とりあえず帰ったら手帳にピンクのペンで書きこんでおこう。光ちゃんが甘えてくれた記念日。だってなんだかそれくらい可愛い彼氏がいとしくてたまらない。だからずっとそばにいてあげたくて、ゆえに私は決意する。もはや即決だった。
「私、今日泊まるよ」
「…ほんまですか」
「うん、ほんとだよ。明日土曜日だし。バイトはあるけど遅番だし。ね?」
こくんっと頷く光ちゃんに、まるで胸を鷲掴みされたような感覚に陥ってしまう。これが俗にいう胸キュンというやつか。そうなのか。思わず頬が緩んでにやついてしまう私に、普段なら「キモい」と毒舌を披露するであろう光ちゃんをどうか見てほしい、まるで小さな幼稚園児のように幼く素直だ。いっそおそろしいほどに。女子はギャップに弱いっていうのはこういうことか。…良かった他の子に光ちゃん送らせたり世話させないで。良かった光ちゃん放置して2次会とか行かないで。妙に上機嫌になった私はにこにこと頬を緩ませたまま、光ちゃんの黒髪に触れてみる。すると彼はまるで撫でられた猫のように目を細めた。かわいい。やっぱり今日の光ちゃんかわいい。こんなの普段じゃ絶対ありえないことだ。
「じゃあ、ぱぱっとお風呂入って寝ちゃお。ね、シャワーだけでも浴びたら頭すっきりするから」
「めんどい……」
「大丈夫大丈夫。お湯溜めないでいいから。シャワーだけでいいから」
むしろお湯を溜めて湯船につかったら、今の光ちゃんではそのまま寝てしまいそうで恐ろしい。お風呂で居眠りして死亡っていうの実は若者に多いって聞いたことあるし、だからシャワーだけだからね光ちゃん。そうなだめるような口調で説得をしていると、珍しく素直で聞き分けのいいらしい彼はまたこくりと無言で頷いた。
「…ほなせんぱい」
「ん?なあに、光ちゃん」
「いっしょにはいりましょ」
「は?」
「ふろ」
「はああああああ!?」
何実は演技だったのやっぱりシラフだったの完全に騙された!いや別に今更ですけど普通に普段だってキス以上のこともしてますから今更ですけど!でも!私お風呂一緒は明るくて恥ずかしいからすきじゃないって知ってるくせに!知ってるくせに!いや、こないだ半ば無理やり一緒にお風呂入らされたけど!でもだからこそ!あれで懲りたっていうのに!
つまり今までのは全部風呂に誘うための酒酔い演技だったのかと疑惑の目を向けてみるけれど、そこでふとお酒の効果なのか妙に潤んでいる光ちゃんの目が合った。…えっ、あれ…?なんか…。どことなく予想の外れた雰囲気をひしひしと肌で感じながら先程とは違う意味で動揺していると、光ちゃんは少しさみしそうな顔で口を開いた。
「あかん…?」
えっちょ、なにやめてって。そんな捨てられた子犬みたいな目しないで光ちゃんただでさえ今日の光ちゃん可愛いんだから、そんな、そんなしょんぼりした顔されたら、わ、私、私、あの、ちょっと。普段は小悪魔みたいに不敵に笑って無理矢理強行してくるドSなくせに、そんな、今日は正反対じゃない。あの、ちょっと、そんな、あの。
「は、入る」
…しまった。どうやら毒に当てられたのは私の方だったようだ。
★
「…………最悪や」
うなだれるような声でそう口にした彼はシャワーを浴びたらすっかり眠気も酔いも醒めてしまったようで、普段のちょっとそっけない光ちゃんに戻ってしまった。あーあ、甘えんぼの光ちゃん可愛かったのに、なんてうっかり口から漏れてしまうと彼はめざとくそれを聞き取ったらしく「何笑っとるん」と不機嫌そうに言った。ふと振り返って見てみるとそこには眉間に皺を寄せた顔をした彼がいたものだから、私はその場をはぐらかすように笑うしかない。そんな私は光ちゃんに借りたスエットを身に纏い、ふかふかのカーペットの上で足を伸ばして座っていた。
「えー。だって、光ちゃんかわいかったのに。きゅんきゅんしたのに」
「…全然嬉しかないねん」
「なんで」
「なんでも」
簡潔にそう答えた光ちゃんは私の背後から、ブロロローッと大きな音を立てながらドライヤーの熱風を私の髪をなびかせていた。光ちゃんはまるで美容師のようにブローするのがうまく、乾かすのも半端なく早い。光ちゃんがやるかやらないかで次の日の朝の髪の調子が明らかに違うものだから、彼の家に遊びに来てシャワーを浴びた後髪を乾かすのはいつの間にか彼の係になっていた。ちなみにそのとき光ちゃんの指が髪に触れるから、私は毎日念入りな髪のお手入れをしている。…なんて事実は勿論彼は知らない。むしろこれは知らなくていい乙女の裏事情というやつだ。
そういうわけだから「光ちゃん、将来美容師になればいいよ」とアドバイスしたことがあるけれど、「専門行ったらと同じ大学行けんやろ」とけろっと返されたことがある。時々光ちゃんは真顔でさらりとデレるから心臓に悪い。まあ今はデレてるんじゃなくて照れてるみたいなんだけど。
「…あーもう。やってられん」
苛立った声が聞こえたかと思ったら、あんなにも部屋中に響き渡っていたドライヤーの音は消え去ってしまった。それを、髪を乾かすことを途中で投げ出されてしまったのかと解釈した私は、「えっ」と驚いているのか困り果てているのか分からない中途半端な声を漏らしてしまう。そんな私の反応を、彼の耳にもしっかり聞こえてしまったらしい。
「…間抜けな声出してなんやねん」
そう怪訝そうな声で尋ねる光ちゃんは不思議そうにしながらもブラッシングを始めたようで、ブラシで毛先を丁寧に梳かし始めた。どうやら髪は乾ききったからドライヤーをオフにしただけらしく、そういえばさっきドライヤー冷風だったなあと思い出す。光ちゃんはいつも熱風で髪を乾かした後は、必ず冷風で髪を落ち着かせる手法をとっている。どうやら最後まで髪の面倒は見てくれるみたいだ。よかった。
「ううん、なんでもない。光ちゃんに髪触られるのすきだなーって思っただけだから」
「…ふーん」
あ。気のない返事をしているように見せかけ、実はちょっと嬉しいって声のトーンだった。長い付き合いなんだからそれくらい分かるよ光ちゃん。不機嫌そうにしているけれど本当は照れているだけなんだってことも、ぶっきらぼうな口調になってしまうのも、不器用なだけで本当は誰より優しいんだってことも、ぜんぶぜーんぶ、ちゃんと分かってるからね。初めて会った中学1年生の「男の子」だった光ちゃんの面影は消え去って今ではすっかり「男」になったけれど、背も随分伸びて、筋肉が全然つかなくて体が薄いって気にしてたのが嘘みたいにいい体になったけれど、それでもやっぱり中身は変わらない。なんだかんだ言ってもやっぱり光ちゃんは光ちゃんで、昔のまんまだね。それがどうしようもなく、嬉しい。
「ふふっ」
頬が緩みすぎて思わず声が漏れてしまった私に光ちゃんは「だから何を笑っとんのや」と眉間に皺を寄せたように問いただしてくるけれど、そんなの素直に答えられるはずもない。「ううん、なんでもないよー」とやっぱり弾んだトーンで打ち返してみたら、すっかり機嫌を損ねさせてしまったらしい。そんなトゥーシャイシャイボーイ光くんはブラシで髪を整えるのを終えた後、まるで私を抱き枕かぬいぐるみのように後ろから抱きしめてはベッドを背もたれにしたまま座り込んだ。「光ちゃん。なんだか今日はほんとうに甘えん坊さんだねー。よーしよし」お腹の前で抱きとめる彼の腕を撫でてはおちゃらけたようにそんなことを言ってみると、案の定光ちゃんの不機嫌メーターを上げてしまったようだった。彼は妙にトゲのあるトーンで反論をする。
「甘えてなんかないっすわ」
「あ、敬語出た!うわーなんか懐かしい!中学のとき以来だね」
「……………」
光ちゃんが黙り込むのは大体バツが悪いときか、自分に都合の悪いことが起こったときのどちらかで、だから大方今のは「やってしまった」とでも思って自分の口を呪っているのだろう。
「あ、そういえば。覚えてる?さっき駄々こねてるときね、私のこと先輩って言ってたんだよ。昔みたいで懐かしかったなーかわいかったなー」
「………………」
あれっ、返答がない。流石にいじりすぎただろうかと彼の様子を伺おうと横目で見やって、そこでふと気が付いた。お風呂から上がって早々光ちゃんは私の髪を乾かす作業に勤しんでくれていたから、彼の髪はまだ湿っているままだ。このままだと風邪をひいてしまう。ところで前々から思っていたのだけれど、光ちゃんはどうしてこうも髪がストレートなのだろうか。天使の輪とかできちゃってるよ光ちゃん。私からしてみたら羨ましいことこの上ないのだけれど、本人にとっては悩みの種らしい。以前「全然嬉しくない」とぶすりと不機嫌そうな顔をしながら、「何もしないと髪がボリュームが出ないから格好がつかない」と不貞腐られたことがある。だから毎朝必死になってワックスやら何やらを使って格闘しているらしい。男の子にも髪の悩みって色々あるんだなあなんてぼんやり思ったことを覚えている。
「光ちゃん、髪乾かそ。風邪引いちゃうよ」
「めんどい」
「めんどいて」
人の髪は壊れ物を扱うみたいに丁寧にブローするくせに、自分のは放置なのか。なんだか呆気にとられていると、光ちゃんはまた眠気が再来したのか私の首元に顔を埋めては、「んー…」なんて、今の私に反応に対する返事なのかそうじゃないのかはたまたもう寝たいという意思表示なのかちっとも分からない実に曖昧な声を出してくるものだからどうも反応に困ってしまう。ていうか耳元で妙にやらしい声出さないでほしい。いや本人は何も考えてないんだろうけれど。それにしても光ちゃんの水分を含んだ髪が首に触れて、つめたい。
だから光ちゃんに抱きとめられたままもぞもぞと180度回転し彼と向かい合う体勢に座り直すと、おもむろに彼の首に掛けたままの少し湿ったタオルでゴシゴシと彼の髪の水分を拭う。「ちょ、なにすんねん先輩」と慌てたように反抗してくる光ちゃんは、きっとまた私のことを先輩と呼んでしまっていることに気付いてはいない。うっかり無意識に出てしまったのだろう。
「さっき光ちゃんが髪乾かしてくれたから、今度は私の番なの!」
「不器用やからええわ。遠慮する」
「光ちゃんが素直に髪乾かそうとしないからいけないんでしょー」
光ちゃんが私にしてくれたやり方とはきっと正反対な乱暴な手付きで彼の頭にタオルを押し当て続けていると、流石に私の手付きが荒すぎるのか、光ちゃんは「痛い痛い」と言ってはうざったいと言わんばかりに固く目を瞑っている。時よりタオルから覗いた彼は子供のようで、でも男の人で、すっかり大人びている。あ、でも味覚は変わってないのかな。相変わらず甘党でぜんざいがすきだし、パンならメロンパン派だし、もっと詳しく言うならチョコチップ入ってないとだめってタイプだし。かっこいいくせにかわいい彼に、愛しさが溢れて止まらない。
「光ちゃん」
無意識にうっかり出てしまった妙に甘えた声で彼を呼べば「なんだ」と言わんばかりに顔を上げてくれる光ちゃんは、やっぱりなんだかんだ言っても素直な証拠だと思う。きょとんと素に戻った一瞬を私は見逃さず頭から少しずり落ちたタオルから覗いた彼の唇にそっと自分のそれを重ねて離れてみれば、一瞬眉間に皺を寄せた彼とぱちりと目が合う。そういえば不意打ちを仕掛けるのはこっちからで十分だと前に光ちゃん言っていたっけ。すっかり忘れていたけれど。至近距離でお互い逸らすことなくじっと見つめ合って3秒後、悪戯が成功したのようにこっと微笑んで声を掛けてみた。
「びっくりした?」
「全然」
そう即答してはくるけれど、明らかにぶすりとして不機嫌そうな彼の目は健在で、つまりそれは驚かされて不服だと言っているようなものだった。光ちゃんは口数が少ないから分かりにくいとサークル内でも言われているみたいだけれど、実際はそんなことはなく、むしろとても分かりやすい方だと思う。負けず嫌いで、人前で努力するのを嫌っているからいつも陰で練習して、無口に見えるのは人見知りが激しいだけで、どこか棘のある言動も本当はその人に気を許している証拠で、つまりはちょっと不器用なだけなのだ。私からしてみれば、いつも周りに気を遣って笑みを絶やさない白石くんのほうが何を考えているのか皆目見当もつかない。
「…今、他の男のこと考えとったやろ」
「うわー、すごいね光ちゃん。なんで分かったの」
「普通否定するとこや」
「うんごめんね普通の子じゃなくて」
「ほんまや。相変わらずキスすんのド下手やし」
「そこ関係ないと思う」
むっとしながら反論すると光ちゃんは意地悪そうに笑うから、やっぱりシャワーでアルコールが吹っ飛んでしまったらしい。光ちゃん節は普段どおりで絶好調のようだ。さよなら可愛い光ちゃん。また会えたら会いましょう。そんな幻みたいな彼に別れを告げて、代わりに目の前の光ちゃんの目をじいっと見つめてみることにする。…酔っぱらったときってその人の本性が出るとか言うけど、ということはつまり甘えんぼな光ちゃんが本心ってことなのだろうか。どうなんだろう。…でもなあ…なんか違うような……。考えてみればみるほど分からない問いに首を傾げていると、その行動をどう勘違いしたのか光ちゃんは妙に楽しそうな顔で口を開いた。
「そんな物欲しそうな顔しとったら襲うけど、ええの?」
うわっなんかさらりとすごい言ってきた。だけど長い付き合いでこういう発言にも免疫ができた私にもう視覚はない。さらりとかわす余裕をこの数年で身につけた私は「はいはいそういうことは髪乾かしてから考えようねー」とやり過ごすことも出来たけれど、なんだかいつの間にか太ももを撫でてくる彼の左手は、きっとそれを許してくれそうにない。風呂場でもさんざんやってきたくせにまだ足りないと言うのか彼は。私流石にもう眠いんだけどなあ。
「光ちゃん元気だねえ」
「どうも」
嫌味もなんのそのと言わんばかりの不敵な笑みに思わずきゅんとした私は、きっと可愛い光ちゃんもすきだけれど、こんなふうに強気な光ちゃんはもっとすきってことなのかもしれない。…って言ったらなんかドMみたいで嫌だな。でもとりあえず私はどんな彼も愛してるってことで、ここはひとつ。だからここは彼の左手に手を重ねて、ついでに愛も重ねてあげようじゃないですか。ね。
20120326 別に事後とかそういう意味でつけたじゃないよタイトル的な意味で←